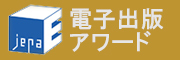最新のAIエディタ『CURSOR』を活用するためのセミナーです。AIによる文章作成というと、まるごと自動生成するイメージがありますが、CURSORは執筆・編集プロセスを変える新しいツールです。AIを活用することで、「まさに自分が伝えたかったものだ」と感じる文章を生み出せる体験が、エディタの画面内で完結します。本セミナーでは、CURSORを使った原稿の執筆やインタビュー記事の編集がどのように変わるのかを紹介します。
申し込みは https://www.kokuchpro.com/event/20250404/
【解説】
本セミナーで紹介する『CURSOR』は、2023年の登場以来、世界中のプログラマから高い支持を受けているコードエディタです。Windows、MacOS、Linux向けに提供され、無料版のほか、月額20ドルのプロ版、月額40ドルのビジネス版があります。その最大の特徴は、ChatGPTやClaudeなどの最新AIが統合されていることです。このAIとの統合により、CURSORはプログラミングだけでなく、原稿の執筆・編集やインタビュー記事のまとめといった幅広い文章作成の場面でも優れた使い勝手を発揮するのでした。
日本語ワープロや一般的なエディタが約30年間ほとんど進化しなかったのに対し、プログラミング用の開発ツールは大きく進化してきました。CURSORは、その決定版ともいえるマイクロソフトの「VS Code」をベースに作られています。VS Codeの効率的で柔軟な編集機能は、文章作成においても大きな価値があります。しかし、CURSORの最大の特徴は、そのすぐれた土台の上にAIを統合した点にあります。
CURSORが使用するAIは、ChatGPTやClaudeと同じ言語モデルですが、エディタとの統合によって「AIと共に書く」という独特の感覚を生み出します。執筆中の文章や関連情報(CURSORでは「プロジェクト」として一元管理)をもとにAIが文章を提案するため、ファイルのアップロードや長いテキストのコピーペーストといった手間が不要です。また、エディタ内にAIが組み込まれているため、文の補完や編集結果の反映もボタン1つなのです。
例えば、私はよく範囲選択して「見出しを考えて」「読みやすくして」「××という言葉を使わずに」などの指示を出しています。文章の本質に集中したいときに、余分な手間をCURSORに任せることで、よりスムーズに執筆を進められます。もちろん、文章全体の構成や間違い・不足の指摘を求めて反映させることも可能です。
今後、CURSORのさらなる進化はもちろん、同様に生成AIを統合した執筆ツールも続々と登場するでしょう。現時点では、エンジニア以外の人がCURSORを使うには、設定や機能のカスタマイズがやや難しい面もあります。本セミナーでは、そうしたポイントを含め、私自身がどのようにCURSORを活用しているのかをご紹介します。
事例紹介:文化人類学系執筆でのCURSOR利用
大川内直子 氏(ideafund社長、国際大学GLOCOM主任研究員)
参考リンク
・いま文章を書くのに「CURSOR」を使わないのは損だ
遠藤諭(Satoshi Endo)氏
株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。MITテクノロジーレビュー日本版 アドバイザー。ZEN大学客員教授。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。AIは、アスキー入社前の1980年代中盤、COBOLのバグを見つけるエキスパートシステム開発に関わるが、Prologの研修を終えたところで別プロジェクトに異動。IPA 独立行政法人 情報処理推進機構の『AI白書』の企画協力・編集、『AI白書2023』に執筆。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。
■ 開催概要
日時:2025年4月4日(金)16時~17時半
料金:どなたでも無料
会場:オンライン YouTube Live(定員ナシ)またはZoom(100名)
主催:日本電子出版協会(JEPA)