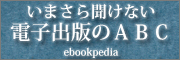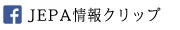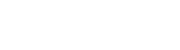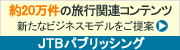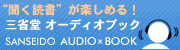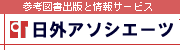本が売れない。この1~2年、私が関わる専門書の分野において、紙の書籍が急に売れなくなった。原因は色々考えられるが、根本的にはお金を払って専門書を買うのを、人々が「躊躇する」ようになったのではないかと思う。ネットを開けばニッチな情報ほど豊富に出てくる。高度な専門情報も例外ではない。書籍のように体系的ではないが、元々、専門書は必要部分のみを読むものなので、こま切れ情報でも支障はない。しかもすべて無料だ。こうなると1冊毎に懐具合と相談しながら「これ買おう!」と決心して高額の専門書を買う理由はないのだろう。
さて、医書の分野では、「医書.jp」という電子配信サイトを出版社が協同で立上げ、書籍・雑誌を豊富に電子配信している。当社もその1社だが、9年前に開始した個人向け書籍の配信サービスが好調で、毎年、売上を伸ばしている。最近、更に好調なのが7年前に開始した病院や大学などの施設向けの雑誌配信サービスである。これは医療関連商業誌、約120誌をセットにして、規模別料金で施設の全員を対象として配信するものだ。このモデルであれば施設に所属する医師や看護師は全コンテンツを無料で閲覧できるので、ネット情報と同様に「躊躇なく」開くことになる。医療の情報は業務で使う情報なので、「施設が費用負担し、読者は無料で読み放題」は理にかなっており、それが歓迎されている様子だ。
施設が費用を負担する以上、施設内の全員に向けた提供が前提になるので、全ての医学領域をカバーすることが求められる。雑誌においては前述のサービスで実現したが、書籍においては全領域のセットモデルは実現していない。値付けや印税の問題、あるいは販売体制や出版社の思惑などから、全部セットは難しい。しかし、それは我々作り手の事情であって市場は必要としているのである。既に海外では概ね同じモデルが実現されており、施設の導入も進んでいると聞く。そのため当該の出版社ではいわゆる印税方式を止めて、雑誌同様、書籍も原稿買取に変更している。問題は技術ではなくて出版社の姿勢なのであろう。
こうした全部セットを施設内の全員に等しく提供するのは、紙媒体では物理的に不可能だが電子なら簡単だ。言わば『デスクトップ医学電子図書館』のようなサービスだが、借りなくてよい、返さなくてよい、閉館時間もない、コピーする必要もない、利用場所を選ばない夢の図書館と言えよう。しかもこの販売や配信に掛かるコストは、個人向けサービスのそれよりむしろ低い。まさに電子出版の本領発揮である。そしてその先に控えているのが、全コンテンツを用いた生成AIサービスではないか。
「本が売れない」時である今、電子出版にしかできない利便性の高いサービスを世に提供することが、苦難の専門出版に明るい光を与えると考えている。いよいよ電子出版に本当の出番がやって来たようだ。