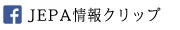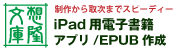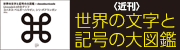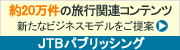私のライフワークとなった電子出版の調査に着手したのは1986年なので、かれこれ36年前となる。振り返ると長い間、富士山の裾野を、頂上と信じる方向に向かって歩いて来た気がする。歩いても歩いても暗い森が続き、先達の歩いた道もなく頂上も見えない。だが、ふと横を見ると、やはり同じ方向を目指す人の姿が見える。その仲間と声を掛け合ってここまで進んできた。そう、それがJEPAの仲間だ。
そんな暗い森を脱し、光が感じられるようになったのは、実はごく最近のことだ。いつの間にか裾野から中腹に差しかったようで、展望も開けてきた。一歩一歩、登って行く実感もある。こうした変化が現れた背景には、皮肉なことにコロナ禍という人類の大きな禍があった。感染防止のため一時は大学の授業もリモートとなり、図書館も閉鎖された。書店で本を手にすることすら危険と思われた。その時に自宅まで配信される医学・医療の情報は、研究者にも医療従事者にも学生にも、大きな利便性をもたらした。コロナ禍で追い込まれてようやく電子の利便性が広範に認識されたのである。
電子出版の理解が進んだのは良いのだが、同時に別の認識も生まれたのではないか。電子と言う便利な道具を使えば情報を得るだけでなく、情報を発信することも容易だ。出版が介在しなくとも、望めば簡単に無料で多くの人に、自分の研究成果や優れた知見を伝えることができる。ことに学術出版においては、著者は印税などの対価より、無償でより多くの人に自分の考えを知らしめることの方を歓迎する。このことは商業出版そのものの存在意義が揺らいだことを意味する。電子出版の価値は広く認識されたが、その基となる出版の存在意義が薄れてきたのだ。
そもそも出版とは何だろうか。出版の役割は何か。出版、それは世の中の多くの情報を取捨選択し、読みやすいように編集し、読み手に届けることだろう。即ち情報をパブリックにすることがパブリッシュ(出版)だ。そこで明治以降、出版社、印刷業、取次、書店などの分業が確立し、それらが有機的に結びついて日本の出版産業が成立、維持されてきた。確かにそうした出版の手法については、その存在意義は薄れてくるかも知れないが、出版はそうした手法を超越した、もっと根源的な役割を果たしてきたはずだ。
今こそ些末な手法論にとらわれず、出版が果たしてきた役割を見つめ直し、新たな時代における出版の役割を見出して行く時だろう。その役割は出版のジャンルによって異なる。例えば海外の自然科学の出版社は、著者が出版コストを負担し、読者は自由に読めるオープンアクセス出版を推進している。これまでの出版とはお金の流れる方向が真逆だが、その変化に躊躇はない。更に言えば、出版は業務全体の一部に過ぎないとし、著者の研究へのサポートを主な業務として行く考えだ。「なぜなら自然科学の進歩への貢献が、今も昔も我々の使命だから」と言いたいのだろう。そんな新たな出版の役割を見出す柔軟さが、今、出版に求められているのではないだろうか。