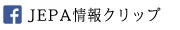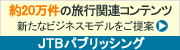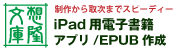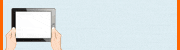大修館書店 飯塚 利昭
小社の英和辞典が電子ブック(EB)として刊行されたのは1995年夏だった。この世界の時の流れの速さは1年が通常の7年分に相当するというdog year説によれば,それ以来,日本人の平均寿命以上の時間がたったことになる。
電子出版に関わる方々にお目にかかるようになったはそのころからだが,そのうちのSさんが「電子出版によって初めて,モノでなく情報を売り買いできるようになったんですよ」と語っていたのが今も印象に残っている。すなわち,書籍の価格のかなりの部分はモノとしての書籍の製造原価であり,それによって価格が決まっているが,電子出版であれば,媒体価格は少しはかかるものの,ほぼ純粋に情報の対価をやりとりできる,というわけである。
その後インターネットによって,媒体価格もゼロということが可能になり,ダウンロード書籍が成立するようになった。
ダウンロード書籍の多くは今のところ「通読する本」である。これについては,価格は情報の対価であるということが,まあわかりやすい。
しかし,辞典などのレファレンス・ブックは,全体の情報量は大きいが,1人の人がそのとき必要とする情報はそのごくごく一部である。「辞書っていうのは,大量のいらない情報を買わされているんですよ。必要な情報だけ買えるようにならないんですかねえ」というのは同じく業界の先輩Y氏に言われたことである。
実際に必要とした1項目の情報の対価だけを払うというのは理屈としては可能だが,たぶん単価はそれほど高くはできなくて,よほど多くの有料アクセスがないと成り立たないだろう。必要とする情報にたどりつくまでに引いた他の項目に対する課金はどうするか,といった問題もある。そしてもっとも基本的な問題は,辞書というのは全体としてひとつの作品であり,個々の項目を取り出したものが即ち辞書というわけではない,ということだろう。
一方で,ネットで無料の情報がいくらでも手に入るという実態がある。情報の対価をビジネスにする上では,この「情報はタダ」という感覚が最大の敵である。
そんな状況を見ていると,結局はまさにコンテンツ=内容というところに立ち帰ることになる。レファレンス・ブックの場合,「ひとつの作品として編集されたこと」に価値を認めてもらえるようなコンテンツを提供する努力を続けたい,という思いを新たにしている。