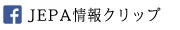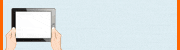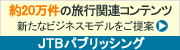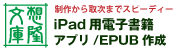パピレス 天谷 幹夫
「あなたはそんなところに、なぜ行ったのですか」、『………』。「だいたい、 こういうところの人は権利ばかり主張して、私らがどんなに苦労しているか 知らないのです」、『………』。「あなたが、そういうことをすると困ることに なるのです。うちは絶対協力しませんからね」、『………』。
某大手出版社の部長は、私が数こと説明しただけで怒り出した。こちらがそんな つもりはなかったと釈明しても、けんもほろろに受け付けなかった。
なぜ怒られたのかよく分からず、四畳半一間の事務所に戻って、二つしかない椅子 の一つに腰掛けて考えても、むしゃくしゃするばかりである。窓際の赤茶けて古ぼけた 年代物の冷房機が、ゴオンゴオンうなっている。この雑居ビルでは、狭いところに100 もの個人事務所がひしめいていて、どの部屋にもこのうるさ型の冷房が備えてある。 ここを借りて会社の登記をしたのは、身もつく寒さの2月であったが、今はうだる ように暑い8月の終わりであった。手帳を取り出して、今までに回った出版社の数を 数えてみたら48社であった。
中には3度も4度も同じ出版社に行ったが、あれこれダメな理由をつけられて何の 進展もなかった。
紙の本を電子化してパソコン通信のホストサーバに掲載して、読者にパソコンで 読んでもらおうという構想を立てたのは、1年前の冬であった。あれからもう1年半 になるのに、1冊の許諾も貰えていない。ビジネスとしてありえないこと、誰にも 受け入れられないことを自分は考えたのであろうか、不安が頭をよぎる。ケンタッキー フライドチキンのカーネルサンダースは、事業資金を集めるのに999人の人に説明し、 999番目の人にめぐり会えやっと受け入れられたという話を思いだし何度も心に言い 聞かせた。どの出版社の協力も得られなかった場合を考えて、著作権の切れた夏目 漱石や芥川龍之介の作品をそれぞれ20冊ほど、外注先で紙の本から電子データに 変換してもらっていた。こんなことをやっているのは、日本でもきっと自分達が初めて だろうと陶酔する反面、こんなに資金を投下して、もし一人も読んでくれなかったら 自分達はおおばか者だろうと思ったりもした。
それなら著者に直接頼んでみようと決心したのが2ヶ月前であった。出版権の2次 利用を許諾する著作権団体があると聞いて麹町の近くのビルを訪れた。何度か訪れ、 構想説明を繰り返して、全面的には協力できないが、実験のためという条件付で数冊 の本を電子化する著作権許諾をようやく貰えたのが先週であった。それで出版社の 了解も取りつけなければと思い、訪れたのが先ほどの大手出版社であった。それが にべもなく断られて、また振り出しに戻ってしまった。
電子データを掲載するホストサーバは、新宿のベンチャー会社が開発したパソコン 通信の電子会議システムを流用することにしていた。電子会議とは、ホストサーバに アクセスした参加者が自分の文章を電子掲示板に書いて、お互いがメッセージを交換 するシステムである。この掲示板に、小説の内容を章ごとに分割して掲載し、順番に 読者に読んでもらおうという計画であった。本当は、電子データをダウンロードする 専用のサーバがあったら良いのだが、それを開発したら数千万円の投資になってしま う。「誰がパソコンで本を読んだりなんてしますか? 本は紙で読むものですよ」と 行く先々の出版社で言われているのに、そんな大きな投資はできない。 システムの 準備は春から進めていて、10月には電子書店を開始しようと計画していたが、肝心 の本のデータが1冊も集まっていない。 心はあせるばかりであった。
それから半月後のことであった。
「いいですよ。これは本当に著者さんのためになると思います」、『はあ……』
「今は、みなさん(著者さん)本が出せなくて、これもあれも品切れになってしまう のです」、『そうなんですか』
「すこしでも著者さんの役に立つなら、うちは別になくてもいいくらいです。 みなさんに話してみましょう」、『ありがとうございます』
中堅出版社の狭い会議室の一室であった。えくぼがくっきりとにこやかな笑いを 浮かべて答えた女性編集長の顔が女神に見えた。事務所に戻る山手線の窓に流れる 景色がこんなにもいきいきと見えたのは初めてであった。それから2週間後、6人 ほどの著者の許諾が得られ、15冊の本が電子化できることになった。編集者と著者 の絆はこんなにも強いものかと感心した。 さらに別の出版社からもシリーズ20冊 の許諾が得られ、電子書店の開始の目処がついたのはその年の11月であった。
電子書店のオープン時には、新しく加わった4人の仲間とともに、狭い事務所の片隅 で喜びの祝杯を揚げた。収益を上げるのに、その後7年以上もかかるビジネスだとも 知らずに……。