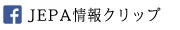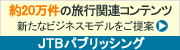■CTSとは……
CTS とは、Computerized Typesetting System の略です。文字通りコンピュータで組版を行うシステムで一般的には電算写植システムといいます。広辞苑にも1991 年に刊行された第四版から見出しとして立項されました。その広辞苑も1983年に刊行された第三版から、それまでの活版組版から大日本印刷のCTS により組版されたという経緯があります。CTS は、1970 年代前半に新聞社や印刷会社に導入されました。新聞業界では、鉛を熱で溶かして活字を作り組版を行うhot type に対するcold type system の略という考え方もあります。
現在のような情報化社会を迎える準備として、当時まだメインフレームと呼ばれ高価な大型コンピュータによる文字情報処理システム導入にいち早く取り組んだ、というのは積極的な動機です。しかし、活版が「鉛」という有害物質を取り扱うことに対する環境問題への対応、また活字を拾って組版を行うという作業者自体が減少していかざるを得ない、といったことが、新聞社や印刷会社がCTS をいち早く導入することの動機として大きく働きました。
一般的には、電算写植システムと言われるCTS ですが、印刷会社の人間には少々こだわりがあります。ひとつは、CTS と電算写植とは異なるという考え方です。CTS は活版の組版ルールをコンピュータにプログラミングしたものであり、電算写植は、手動写植のルールをコンピュータにプログラミングしたものという点が異なります。例えばCTS の活字の寸法の単位はポイント(1 ポイント= 72 分の1 インチ、約0.35 ミリメートル)ですが電算写植のそれはQ 数(1Q = 0.25 ミリメートル)となります。また文字についてもCTS は活版を継承し、書体が少なく文字数が多い。これに対し電算写植は手動写植を継承し、書体は豊富だが文字数が少ない。結果としてCTS の最も威力を発揮する品目は、辞書・事典、古典物、名簿ということになり、電算写植は、商品カタログということになります。
もうひとつのこだわりは、CTS には狭義のCTS と広義のCTS があるという概念です。狭義のCTS とは、文庫本のような文章の組版を行う「一般組版」として、先に述べた活版の組版ルールをコンピュータに置き換えたシステムのことです。広義のCTS とは、「漢字情報処理」「文字画像情報処理」などと呼ばれ、コンピュータによる組版とデータの加工処理を合わせた情報処理体系全体を指すシステムの概念です。
■業務効率と付加価値
コンピュータは、そもそも大量データの並べ替えやある特定の言葉を抽出をするという仕事が得意です。これら並べ替えや抽出の機能を果たす別建ての情報加工処理用のコンピュータを駆使し、辞典の項目の五十音順の並べ替えや膨大な索引処理を行い、その加工処理後のデータを組版用コンピュータに引渡すことで素早く大量な組版をすることができます。また、次回の改訂作業に向けた有効なデータを保存することが可能となります。
さらに、例えば図版や写真も取り込んだり、電算写植の豊富な書体を使うべく、電算写植用の写植機で版下出力をすることも、この広義のCTS に含まれてくるのです。この広義のCTS の最も威力を発揮する品目は、大型の辞・事典や分厚い名簿、会社情報誌やテレビ番組表といった情報誌があります。辞・事典ではそれまで印刷所に対し、原稿をあいうえお順に入稿することが必要でしたが、著者別、分野別入稿などランダム入稿が可能なり、結果として辞・事典の製作期間の短縮が可能となりました。情報誌ではその命である、より新鮮な情報の掲載ができるようになりました。
CTS は、文字や画像をデジタル化することに始まり、そのデジタル化したデータをコンピュータで組版することにより、それまでの熟練工の作業をオペレータのレベルまでにブレイクダウンし、出版物の製作プロセスに変革をもたらしました。これがやがて1980 年代後半からのDTP の世界に引き継がれていきます。
一方、デジタル化したデータとそこに様々な加工処理を施すCTS の技術は、冊子の編集・製作業務に対して、人手の作業だけでは途方に暮れてしまうような出版物をスピーディに作るという「業務効率」を与えてきました。また、同時にデジタルデータそのものに対し、いかようにでも料理されることを待ち望んでいる素材のような「付加価値」を与えてきました。そしてこれら「業務効率」と「付加価値」を提供する機能は、1980 年代後半から始まるニューメディア時代、マルチメディア時代に向
けてCTS の夢として花開いていくことになります。
◎野村虎之進(のむらこうのしん)大日本印刷からJEPA に参加。