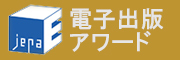写研とは
1926年に写真植字機研究所として創業、現在はデジタルフォントの開発・販売、不動産賃貸・管理を事業とする日本の企業。DTPが普及する2000年代初頭以前には、写真植字機と組版等の関連システムと書体の製造・制作、販売を一体として行っており、優れたハードウェア、システム、書体デザインをトータルで提供する写真植字の業界最大手であった。日本のタイプフェイスデザインは写植の時代に大きな発展を遂げたが、その中でも写研が果たした役割は大きい。しかしながら、DTPに対し消極的な姿勢を取り続けクローズドな自社専用システムに拘り続けてきたことなどから、DTPの普及とともに急速にその地位を失うこととなった。
もっと詳しく!
写真植字(写植)とは、DTPが一般化する以前に広く用いられていた文字組版の技術である。複数の字母がネガの状態でまとめられた文字盤からレンズを通して光学的に印画紙、フィルムに文字を焼き付けて版下を作り、オフセット印刷で印刷を行う。金属の鋳造による活字を用いた活版印刷に対し、光学的処理により文字のサイズ、文字詰め、変形(長体、平体、斜体など)などの自由度が高く、DTP普及以前には文字利用の場面で写植が幅広く使われていた。1960~80年代にかけては、写植用に多くの優れた書体も開発され、グラフィックデザインにも大きな影響を及ぼした。写研は、日本における写植の代表的な企業であった。
写研の写植機
-
手動写植機
手動写植機では、文字入力と組版が一体化しており、1文字ずつ文字を入力しながら同時に組版を行う仕組みとなっている。
本格的実用機としての石井式写真植字機は1936年に製作された。18本の主レンズと拡大アタッチメント2種を備えることで文字サイズ7~60Q(1Q=0.25mm)に対応。変形レンズ3種、文字盤収容数35枚、ルビ印字機能も備えていた。国内のみならず、満州・朝鮮・中国・ジャワ・タイ等にも納入された。
1960年代以降には、和文タイプライター程度に小型軽量化した本文専用機SPICAシリーズ、組版を電子制御で行うPAVOシリーズが手動写植機として開発される。1983年に発表されたPAVO-KVでは、搭載したCRT表示装置に組版の様子を全面表示させることを可能としWYSIWYG(What You See Is What You Get:最終的な仕上がりを画面上で確認しながら作業できる)の先駆けとなった。
-
電算写植機
組版作業をコンピュータで自動的に制御する、日本初の電算写植機が写研のSAPTONシステムである。1966年に新聞社向けの写植システムとして全自動写植機実用機SAPTON-N3110が開発され、以降、ミニコンピュータに組版ソフトウェアを搭載したSAPTON-Aなど一般印刷向けにも広がっていった。
1970年代後半には、CRT上に文字を出力して露光する方式により印字を高速化したSAPTRONシリーズが開発され、1977年に発表されたSAPTRON-APS5ではデジタルフォントが搭載された。
1980年代には、アウトラインフォントを搭載し、文字と画像を一括して出力するレーザー出力機(製版機)SAPLSシリーズ、WYSIWYGを実現したSAIVERTシリーズなどが開発される。2000年には、WindowsNTベースの組版システム「Singis」が発表されたが、以降、新機種は発表されておらず、これが写研写植機の事実上の最終機種となっている。
写研の主な書体
1960年代から1990年代にかけて、写植が文字組版の主力技術であった時代には、写研の書体は、書籍以外にも、市場を大きく拡大しつつあった雑誌やコミックで広く用いられるとともに、ポスターやチラシ、テレビのテロップや道路標識、家電等の表示文字など、様々な媒体、場面に使用された。写研が開発した代表的な書体の例を以下に挙げる。
-
石井書体
写研創業者である石井茂吉氏は、自身で書体のデザインも手掛け多くの書体を制作している。初期の石井式写植機から搭載され後世に残り広く用いられることとなる石井明朝、石井ゴシックといった基本書体以外にも、石井丸ゴシック、石井ファンテール、石井宋朝、石井教科書など、いずれも高い評価を受け、その後の書体デザインに大きな影響を与えている。
-
ナール
写研主催の書体コンテスト・石井賞の第1回(1970年)で1位となった中村征宏氏による書体。ふところの広い極細のモダンな丸ゴシックで、1970~80年代の雑誌(特に女性誌など、オフセット印刷の普及に伴い数多く出版されたグラフィック系雑誌など)の本文やポスターなどの印刷媒体で広く使用されたほか、視認性が高いため、看板、道路標識、鉄道等のサインシステムなどにも多用された。
-
ゴナ
ナールのデザイナー・中村征宏氏による特太角ゴシック体。欧文書体にみられる直線的・幾何学的な輪郭が特徴で、見出し用文字として広告や雑誌に多用された他、高速道路の案内標識などにも使用された。「モダンスタイル」と呼ばれるゴシック体として、後発の書体デザインに大きな影響を与えた
-
スーボ
第2回石井賞を受賞した、極太丸ゴシックのディスプレイ書体。当時、写研の社員であった鈴木勉氏がデザイン。これまでの書体にはなかった、画線の重なり(くいこみ)が特徴的であった。
-
本蘭明朝
1970年代ごろから普及してきた自動写植機に対応した書体として、書籍、文庫などの本文用に新たに設計された。かなのデザインは橋本和夫氏。石井明朝に比べ字面が大きくふところが広め、画線の強弱が規則的に整理されてモダンな表情を持つと言われる。
なお、写研が保有する書体は下記のサイトで見ることができる。
写研出身の書体デザイナー
写研からは、現在のデジタルフォント環境においても国内外で活躍する多くの著名な書体デザイナーが輩出されている(以下、敬称略)。
橋本和夫:写研で約30年にわたり文字制作責任者として書体開発の総指揮を執った後、イワタ社にて書体デザインを指導。
藤田重信:現在、フォントワークス社で筑紫書体を始めとする書体デザインを手掛ける。 鳥海修、鈴木勉(故人):写研を経て字游工房設立。ヒラギノ書体、游書体の設計に携わった。
今田欣一:写研にて、ボカッシイ、ゴカール、今宋などを開発。独立後、欣喜堂ブランドで、きざはし金陵、さくらぎ蛍雪など多くの書体を設計。
小林章:写研を経て渡英後、欧文書体の国際コンペティションで2度のグランプリを受賞。現在、ドイツMonotype社クリエイティブタイプディレクター。ヒラギノ書体、AXIS、たづがね角ゴシックなどを手掛ける他、企業ブランド用書体の制作や欧文名作書体のデジタル環境に適した改刻などを行う。
写研書体のOpenType化
電子書籍が普及し始めた2011年に、自社システム以外では写研書体を使用させないというそれまでの方針を変更し、写研フォントのOpenType化を進めることが発表されたが、結果として実現には至らずに終わっていた。その後2021年に、国内フォント事業最大手のモリサワから、写研との共同事業として写研書体のOpenType化を進め2024年から順次リリースを予定していることが発表されている。
モリサワ OpenTypeフォントの共同開発で株式会社写研と合意 |株式会社モリサワ
参考
『技術者たちの挑戦 写真植字機技術史』布施 茂 著(創英社/三省堂書店)